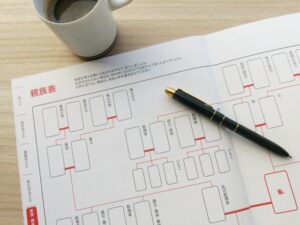財産目録の作り方 ― 相続で混乱しないための準備ガイド
相続の相談を受けていると、「親の財産がどこにあるのか分からない」「書類が散らかっていて、相続人同士で揉めてしまった」という声を多く聞きます。
そんなトラブルを未然に防いでくれるのが “財産目録(ざいさんもくろく)” です。
財産を“見える化”することで、相続手続きが驚くほどスムーズになり、家族間の争いも避けやすくなります。
今回は、誰でも作れる財産目録の基本から、行政書士としておすすめする作り方・注意点まで、分かりやすく解説します。
1. 財産目録とは?作る目的とメリット
財産目録とは、所有している財産(+必要に応じて負債)を一覧にまとめたものです。
法的に作成義務はありませんが、以下のメリットが大きいため、相続対策では必須の書類と言えます。
● 主なメリット
- 相続財産の全体像が分かる
- 相続人同士の認識ズレを防げる
- 遺産分割協議が早く進む
- 預貯金・不動産・保険などの漏れを防げる
- 認知症になる前の備えとして有効
特に、財産が複数の金融機関にまたがっている場合、目録があるかどうかで手続きスピードが大きく変わります。
2. 財産目録に必ず入れるべき3つの区分
財産目録は、以下の3区分に分けると非常に分かりやすくなります。
(1)プラスの財産(資産)
- 預貯金
- 現金
- 自宅・土地などの不動産
- 自動車
- 株式・投資信託
- 生命保険(受取人が相続人以外の場合は注意)
(2)マイナスの財産(負債)
- 借入金
- 住宅ローン
- クレジットカードの残高
- 未払いの医療費・税金など
※負債も必ず書くことで、相続放棄の検討が必要かどうか判断できます。
(3)その他の重要情報
- 印鑑の保管場所
- 通帳の場所
- 保険証券・契約番号
- ログインID/パスワード(別紙管理がおすすめ)
- 貸金庫の有無
これらを整理するだけで、家族は驚くほど手続きが楽になります。
3. 財産目録の作り方 ― 初めてでも簡単にできるステップ
行政書士が実際にアドバイスしている標準的な作成方法です。
ステップ1:書類を集める
まずは自宅にある資料を集めます。
- 通帳・キャッシュカード
- 登記簿謄本(不動産)
- 保険証券
- 証券会社の取引報告書
- ローン契約書
- クレジット明細
最初は「ざっくり」でOKです。
ステップ2:財産を項目ごとに書き出す
財産のジャンル別にシンプルに記載します。
例:
預貯金
・○○銀行 本店 普通 1234567 残高:1,200,000円
不動産
・福岡県○○市○○町1-2-3
地番:○○ 土地150㎡
固定資産税評価額:800万円
ステップ3:負債も正確に記載
債務は隠さず記載するのがポイントです。
例:
・△△銀行 住宅ローン残高:6,200,000円
ステップ4:定期的に更新する
財産目録は“作って終わり”ではありません。
- 年に1回更新
- 財産を処分した時
- 新たに口座を開設した時
最低でもこのタイミングで更新しましょう。
4. 財産目録を作るときの注意点(行政書士が見た実例より)
① メモ書きだけだと相続で使えないことがある
金額の記載なし・口座名義不明など、曖昧な目録は相続では役立ちません。
② ネット銀行・ネット証券を忘れがち
多くの相続トラブルの原因がこれです。
③ 不動産の評価を“固定資産税評価額”で統一する
時価は曖昧になるため、目録には統一基準が必要。
④ パスワードを目録に直接書かない
セキュリティ上、別紙にして保管場所だけ記載するのがおすすめ。
5. 「財産目録」を作っておくことで相続は確実にスムーズになります
財産目録は、家族の負担を減らすだけでなく、
“争族”を防ぐ最も簡単で効果的な相続対策です。
- 何から手をつけてよいか分からない
- まずはフォーマットを作ってほしい
- 財産の整理と相続対策を同時に進めたい
こういったご相談も行政書士として日々お受けしています。
福岡県内で相続の準備や生前対策をお考えの方は、ぜひお気軽にご相談ください。